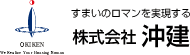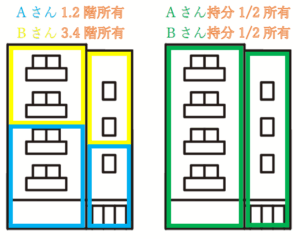深刻化する空き家の倒壊!その責任は?事例を見る!

空き家の放置問題が深刻化しています。衛生、環境、景観、そして防災という観点から、周辺住民の生活環境を脅かすことになるとして、行政も動き、2015年5月26日、「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特別措置法)」を施行しています。この法律で「特定空き家」と認定された空き家の所有者は罰金などが課せられます。相続などで空き家を所有することになったものの、放置状態にあるという事例が少なくありません。しかし、倒壊すればご自身だけの問題ではなくなります。その事例を見ていきましょう。
空き家を放置するとどうなる?

「家を相続したけれど、引っ越す予定はない」「高齢化した両親と同居することになり、実家が空き家になってしまった」など、空き家になってしまう理由はさまざまです。しかし、空き家のままで放置するとさまざまなリスクを抱えることになります。
- 資産価値の低下:空き家となって建物の老朽化。資産価値が低下し、売買等が困難に。
- 倒壊:空き家の傷みが進むと、倒壊してしまう危険性が増加。
- 外壁落下:外装材や屋根材などの破損が進み、落下する危険性が増加。
- 害虫、害獣の発生:ねずみや害虫などが大量発生して、不衛生な状態に。
- 景観の悪化:ごみの散乱、山積みや外壁の破損・汚損などで景観を損ねることに。
- 悪臭:腐敗した動物の糞尿やごみなどが放置され、悪臭が発生。
- 不法侵入:不法侵入者の出入りで、周辺地域の治安が悪化。
また、空き家を放置し、庭木の手入れもしていなかったことで、隣の敷地や道路などに枝がはみ出し、周囲の建物を傷つけたり、歩行者の通行を妨げてしまったりしまうこともあるでしょう。こうした空き家は迷惑な物件として、ワイドショーなどでも取り上げられることもあり、目にされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
倒壊の恐れで危険な空き家の事例を新聞やテレビが報道
倒壊の恐れがある空き家が増加し続けており、「特定空き家」として認定された空き家が行政代執行で解体処理された報道もあとを絶ちません。
読売新聞が報道した2025年3月に実施された福山県勝山市の事例
福井県勝山市で2025年3月、空家対策特別措置法に基づく「特定空き家」に認定された住宅が略式代執行で解体処理されたことが報道されました。処分されたのは勝山市内の住宅街にあった、壁が腐食した木造2階建て住宅。この住宅の居住者が2014年に亡くなり、2年後の2016年ごろには近隣住民から倒壊の恐れあり、と市に苦情があったのだそうです。調査結果で相続人がいないことから、
相続人がいなかったのだそうです。2年後には近隣住民から「倒壊しそうだ」と市に苦情が入った。市は亡くなった方に相続人がいないことを確認し、略式代執行。約250万円の住宅の解体やがれき撤去の費用は市が国や県の補助を活用して負担したということです。市の担当者はこの件についての取材で「例外的」とコメントされています。福井県内の特定空き家の認定件数は20年3月時点で累計248件が2024年末には、60%増398件。問題は深刻化の一途を辿っています。
名古屋市でも行政代執行、200万円を所有者に請求との報道
一方、名古屋では2025年1月、倒壊の危険がある名古屋市中村区の空き家が行政代執行で解体処理となったことを東海テレビが報じました。この空き家の所有者が撤去命令に応じなかったことから市が行政代執行を行ったということです。解体費用の約200万円は名古屋市が一時的に負担しますが、所有者は市から請求されることになります。
名古屋市でも空き家が増え続けており、東海テレビの報道によると名古屋市内には倒壊や衛生面で悪影響を及ぼす特定空き家がおよそ30戸あるそうです。
空き家が倒壊すれば責任を追及されます!

空き家問題を重くみた政府は2015年から「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特別措置法)」を施行しています。この法律によって「特定空き家」に認定されてしまうと所有者は様々なリスクを負うことになります。
「特定空き家」に認定されるまでのプロセスは?
「特定空き家」の認定は、指導・勧告・命令という段階的なプロセスを経て行われます。多くの場合、近隣住民からの苦情や情報提供、市町村の職員による定期的な地域の巡回などで、管理不全と見られる空き家が発見されると、現地調査や不動産登記簿などの調査が行われ、空き家の所有者が特定されます。
その後、特定された所有者への連絡・指導が行われ、口頭や文書による指導となります。この指導に従わない場合や、状況が改善されない場合、市町村長名で改善に向けた勧告が行われます。この段階にくると、建物があれば減額されていた固定資産税の特例が解除されてしまうかもしれません。
また、勧告後も改善が見られない場合、危険性が高いと判断される場合に、市町村長名で必要な措置が命じられます。そうなると行政代執行につながってしまうのです。そうなる前に所有されている空き家の処理を考える必要があります。
特定空き家となった空き家が抱えるリスクは?
空き家のまま放置し続けた場合、次のようなリスクに直面することになります。
- 固定資産税の住宅用地特例が解除される恐れ
- 所在地、所有者氏名など、認定された空き家の情報がウェブサイトや広報誌などで公示される可能性
- 50万円以下の罰金
- 行政代執行による強制的な解体処理と費用請求
空き家倒壊の場合、所有者に賠償責任が発生する可能性は?
「倒壊した空き家の一部が隣の家屋を損壊してしまった」「倒壊した空き家のがれきが道路に散乱して、通行人に怪我をさせてしまった」「空き家が倒壊の際に飛散した部材が近隣住宅の所有物を破損させてしまった」
空き家は多くの場合、所有者が管理を怠っている状態です。こういった場合、民法という法律によって、空き家の所有者が被害者に対して賠償する責任が生じてしまうことが多いのです。
国土交通省が主管する団体で住宅・宅地に関する調査研究や情報の収集・提供を行っている公益財団法人の日本住宅総合センターが空き家に関する損害賠償リスクについて試算しています。その中には空き家が隣家へ向かって倒壊し、隣家が全壊を想定し、住人の主婦と子供が死亡した場合として損害額は2億860万円という金額を出しています。
空き家の放置を続け、倒壊した場合、こうした賠償責任を負う可能性もあるのです。
空き家は放置しないこと!管理できないなら売却も?

空き家を管理せず放置状態にしておくと、特定空き家となってしまい、所有者であるご自身のリスクとなります。また、放置状態の空き家が倒壊した場合にはその賠償責任を負う可能性も高いのです。
建築基準法の改正で空き家のリフォームは困難に
放置状態で所有し続けた場合のリスクを考え、相続された空き家を売却したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
2025年4月1日、改正建築基準法が施行されます。この改正では防災や環境負荷低減といった側面からリフォームに対する条件が厳しくなります。空き家が改正によって改正法の基準に合致しなくなってしまった既存不適格建築物を適法物件にさせるためのリフォームにはコストアップするだけでなく、要する時間が増えるでしょう。また、改正前から再建築不可物件だった空き家はリフォームが困難になってしまいます。
そのため、今後、リフォームを要する物件の売却は困難になっていくことが予想されます。
買取専門の不動産会社への売却も視野に
改正法の施行で空き家に対する締め付けはますます厳しくなるでしょう。そこで処分の相談先として考えられるのが買取専門の不動産会社です。買取専門の不動産会社は訳ありの物件や事故物件などの仲介では売却が困難になるケースが多い物件も取り扱っており、ノウハウもあります。空き家の処分について検討されているのであれば、買い取りを専門としている不動産会社への売却も視野に入れ、相談されると良いのではないでしょうか。
空き家が倒壊する前に、まずは沖建にご相談を!
空き家問題の解決に向けて、政府や行政機関は様々な制度を導入しています。空き家の放置で衛生上、環境上、さらには安全上の問題が拡大していくからです。そうした中、2025年4月から施行される建築基準法の改正でリフォームも難しくなっていくと予想されており、これまで以上に売却は困難になるでしょう。所有されている空き家物件が倒壊してしまう前に、特定空き家に認定されてしまう前に、そうしたリスクを解決していくことが重要です。弊社沖建は一般的な不動産会社では扱いが難しいような不動産物件で数多くの買い取りの実績がございます。所有されている空き家でお悩みの際には私ども沖建グループにご相談ください。さまざまな角度から検証し、売主さまに対してベストだと思っていただける提案を出せるよう、弊社スタッフがご対応させて頂きます。